蟲
気付きが産まれたのは今回での出来事さ。
地下牢を思わせる回廊入り口。
『アキツグ様! 』
掛けられた声に反応することも無く私の左腕は転がったのさ。
生来痛覚と言う物が私には無いに等しいのでね。
左腕を落とされたわけよ。
私も無限に続くと思うやり取りに食傷気味になっておったのでね。
良いタイミングにして好機に変わったわけさ。
私の左腕を落とした獣はあっさり撫子に討たれたのさ。
「お兄ちゃん…… 」
撫子が捥げた左腕を私へ持ってきた。
「どれ…… 」
ソレを受け取ると、左腕を筆にして曲を流そうと思ったのよ。

「幻想曲とは、芸術の域を染み入るな…… 」
この曲は素晴らしく気に入っている。
曲の静と動をピアノ一つで再現し、感情の奥底を振るわせる主旋律がこの回廊の全てを多角的に彩るのさ。
「お兄ちゃんの腕…… 蟲さんが集まってるよ? 」
この一言が大きかった。
蟲使いではない私なのでね。 視線を血に塗れた楽譜にやると異形の蛭が這い回っておるのさ。
「蟲は好かんな…… 」
寄生されていた……?
いつの間に? そう思わず点と線が繋がったのは言うまでもない。
「くはは…… 当主も一服盛られておったと言うのか? 」
猫のような口元をしたまま、撫子は私を見ておるが説明は不要。
「撫子よ、お前は良い女子として育ったものよ 」
『…… 』
アーニャには悪いが、今回撫子は大儀であるのさ。
「アーニャ! 糸を縦に張り撫子とお前は結界の中で待て! 」
『ダー 』
左手、右手と上下に振り下ろすとアーニャは良く切れる縦の糸。
そして守りの結界を、回廊入り口に張り巡らせたのさ。
無限の仕組みはこれかよ……
臨兵闘者…… 左腕を地面に押し当てて円を書く。
「三つ指着かんで良い…… 」
この白い着物の女は朧と言うのさ。
視線の合った生き物を死ぬまで焼き続ける怨念の塊よ。
私だけは死なんのだがね。
「朧…… 私を焼け! 」
正座を崩さず三つ指着く女は首を横に振るのみ……
私を囲む人外、魑魅魍魎をその場で見ては焼き殺す。
「よかろう…… 朧よ。 この鬼の群れを任せる 」
ここでやっと立ち上がるのだから、女の気持ちなど一生解らんと思ったのさ。
マッチ棒一本擦りあがった小さな仄暗い闇が何処かの鬼畜へ燃え上がると、そこからは太い鎖で重く繋がれた囚人達の終わらない叫びが始まったわけさ。
「見れば炎の揺らめきにも、風が舞い降りる水面のようにも見えるのに、この闇にはどのような仕掛けがあるのだろうと今もなお考えてしまうな 」
得体の知れぬものほど、想像を掻き立てられて必要以上に美化してしまうのかも知れんな……
もう一度この深い深遠の闇に飲まれようとはしたくなかったが……
『アキツグ様! 』
呪イ
胸の前で手を組むアーニャの顔色は不安が窺える、これも胸が痛むのだが逝くしかないと思うのでね。
仄暗く揺らめく闇に蝕まれ焼かれていく鬼の群れに飛び込んだのさ……
塵になるのに待たせるほどでもない。
声を上げず私を巻き込んだ事に気付いた朧は体を落とし全身で泣く。
その泣き声が子守唄となり、燃え尽きた塵の中より私は産まれましたとさ……
着物が消し炭にならんのも不思議だが恥を欠かぬで良いな。
「泣かないで良い 」
朧の頭に手を置き、振り返り無限に続くであろう廊下を見てみると景色は変わり果てたのさ。
「これはこれは…… 」

赤い札、黒い札。
動物共の屍骸。
白と黒の勾玉。
麝香。
無限に続く廊下は呪詛と嘘で固められたものだったのさ。
体に寄生された蛭と効果を発揮してここまで無限の廊下と感じさせるとはね。
呪いに掛かるというのは良い体験をしたかな……
「無限無きこの廊下、魑魅魍魎の巣窟は変わらぬのだな 」
押し寄せる獣の数も人外も変わらず奥からここを目指してくるのでね。
無限の謎を解いても無数の悪鬼共の湧き出る様が解決せぬのだと……
入り口を四枚の和紙で封印するのよ。
四神の守りというものさ。
「白虎、青龍、朱雀、玄武。 私の戻るまでここを閉じろ 」
簡単だろう?
封印などこの程度のものさ……
「さあ…… 当主の下へ戻ろうか。 朧戻れ…… 」
尻もちしたまま右手を地に着けて左手の裾で顔を隠し消える。
華の在る寂しさを残した消え方であったとさ。
「おう! 久我。 どうであった? 」
その男は状況を気にする素振りは無く、ただ笑顔を無防備に晒したのさ。
右足膝を立てて右手を曲げると当主は声を上げた。
「回廊の疑問は解けたぞ…… 」
そう言い放ち私達も、広い部屋で無造作に座り込んだわけよ。
当主は酒を飲み、運ばれた飯を喰らい一息ついて言うのさ。
「久我の最高傑作とは聞いたが、俺に解明出来ぬ事由を鮮やか過ぎる 」
「私も盲点であったさ。 当主よ。 盛られておるぞ? その女にな…… 」
当主は眉すら動かさず口を開いたのだ。

「リンドウ…… あれは俺の愛した女が匿った異国の女よ 」
その女を疑いたくも無かった。
そして俺の愛した女の愛を、あの女にも教えたかったのさ。
可笑しいとは思っておったさ。
息子…… 八千代は力を持つといっても、引きつけるだけ……
蛇であろうが、鬼であろうが人外を呼んでしまうだけ……
俺が切り殺すだけで済む話が、気付けば中庭から八千代は動かず。
顔を頬を撫でることも叶わない距離に離れた。
新しい力と思いもしたが、リンドウがこの家の一人と受け入れられる頃。
無限に続く回廊と、人外の群れは悩みの種になったのだ。
それは納得のいく道理で、薄々は考えておった一つではあった。
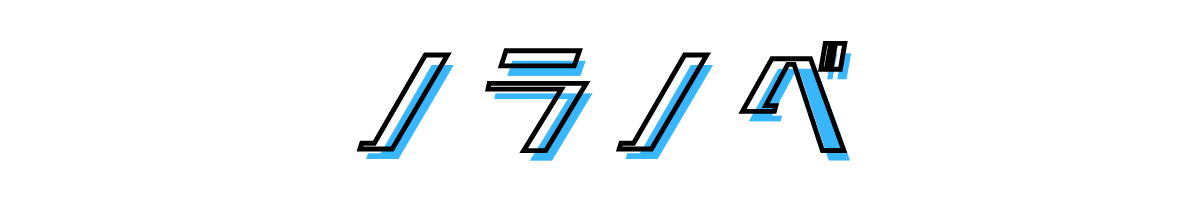


コメント