戦イ
ふむ? 一尺先すら見えぬ闇夜、山道を童の母様探すとなりては折れるものがあろうな。
麓へ行くまでのこの道は獣アヤカシ潜む予感。
解らんでも無い、女を求め飢えたオスがここを上るのだろう?
寸前で止められた欲望の膜ほど張り詰めて成熟したものは無いのかもしれん。
そうさな……
予感が当たるからこそ、この闇の中私は人の顔を持った犬の生き物の群れに囲まれておる。
普通の男子なれば此度の、あくしでんとで絶命しておるの。
解らんでもない数。 立会い終了だな?
抜かせておくれ。
私を囲んだ人の顔共よ、私の四肢が欲しいのだろう?
アーニャが認めるならくれてやるともさ。
こんな不死身の体など……
肩幅に広げた足は、十束剣を振れる体勢。
十数匹からなる人の顔の畜生は、私の剣筋等見る事無く椿の花と同様に根元から……
そう根元から、ぼとりと重力と友になり、首から顔は逆らわず地面に接吻した。
「愉快だな。 これはまた脆い結末にして愉快よ 」
私と関わらなければ良かっただけの一振り、元言えば一幕だのに……
「椿の花が土に還る、もはやそのような無駄は栄養ではないな 」
私の一張羅は鬼との戦い以来汚れ一つ無い。
「良い夜だ 」
見上げる闇夜は雲一つ無く、月明かりが山中の獣道を照らしている。
今度は腹を空かせた狼が私を囲む、麓はまだかと退屈にもなる。
気にもせず狼の群れの中、道を進むが剣を持つ左腕が軽くなった。
「あぁ、左手をもっていかれてしまったか 」
地面に蘭丸が落ち、左手首から下の肉を狼は銜えてこちらを睨んだまま。
「血で汚れるのも面倒でな 」
左腕のシャツをまくり、私の腕を銜えた狼に近づいた。
「食い終わる様を見てやろう 」
群れの狼はまず一匹だけが私の腕を食い始めた。
群れは私を遠巻きに囲み、中心はこの狼と私だけの空間に変わった。
狼は食事を途中で止めて、左手の再生された私に近づいてくる。
犬の気持ちなど解らんが腹が減っているのは理解できる。
「与えてやるものが無くてな…… 」
近づいた狼が私の元へ来たのは何故かは問うまい。
右手で頭を撫でてやり、狼の肩を左手で抱いてやった。

「人の味を知る獣はまた人を襲うからな 」
撫でた右腕を口元まで這わせて、上顎と下顎を魚の開きのように広げてやった。
なに、一瞬なのでな。 声もあげる事無く狼は絶命したよ。
靴底の硬い私のブーツで横腹を蹴り飛ばし、群れに投げ込んでやる。
「用意出来た飯などそれくらいでね…… 」
人間が人間を喰うくらいであるからな、狼が狼を喰っても不思議など無い。
嘘を覚えた人間が繰り返すように、味を占めるというのは真に醜いな。
「ほう…… 」
一刻経たぬ内に裏山の麓についたのさ。
絶景かな、絶景かな…… 並んだこけしの様な植物はケシ坊主であろうな。
「どれ観えるかな 」
月明かりに照らされた花の大平原、風が花弁を舞わせ二度三度空へ誘う光景が現実を忘れさせるな。 幻想的ではある。
ケシ坊主が風に波打ち揺れる花の海原に、黒い月が目の前遠くに見付ける事が出来る。
「大きいな、桶とはあのことか? 」
三尺程の木の樽に見えるのだが、中には人だった者が私を見つけたようだ。
艶のある黒髪を左から右に寄せて、右半分顔を隠すような髪型は花魁や遊女と解る美女と言う物だったろう。

ソノ姿ハ
「陰陽師の方でありんすか? 」
「廓詞(くるわことば)初めて聞いたな。 陰陽師等でもない 」
気品あるように座ったままのそれだが殺そう。
そう決めるには十分なケシ坊主に囲まれている。
「着物脱いだほうがよいでありんすか 」
裸になり立ち上がろうとするそれに引き金を二度引いた。
「寄るな下衆 」
裸の女を見るのも興味も無い。
桶の女は打ち込まれた弾が本物だと解り震えて失禁した。
その顔は恐怖で歪む事無く、欲望満たされた表情で私を見上げ股を開き失禁を繰り返す。
「阿片で狂っておるのか、梅の花で壊れたか? 」
私のピストルの音と桶の床に打ち込まれた弾を見て女は絶頂し体を震わせる。
「あちきを良い人にして欲しいでありんす 」
太股まで湿らせた体を私に向かい見せてくる。 肌が立つ瞬間だな。
蘭丸を使うのを躊躇いたかったが、感情のまま隠してる髪と皮膚を落とした。
「ふむ、梅の傷だな…… 」
右側の顔は鮮やかな色をした梅の花が咲いている。
切り付けられても女は失禁し体を痙攣させる。
「おいおい、美しい顔も血だらけのようであるぞ? 」
血という言葉に反応したソレは両手で顔を拭いた、掌を確認するとようやく自身の血に気付き泣き始めた。
「あちきが何をしたでありんす? 」
「知らんよ、聞かせておくれ 」
「あちきが何をした? 」
「だから知らぬから最後に聞いてやるとも 」
右の顔に咲いた梅の花を落とした。
流石に痛むようで、桶から出て絶叫。
ケシ坊主の熟れた実に滲んだ液体を、舐めてすくいあげ飲み干し、口に含んで上下させ喉を鳴らす女がおる。
そして女は一面にある、ケシ坊主の実から出ている液体を何本か飲み込んで落ち着いた。
「あちきは死にたくないでありんす 」
「殺されるとは解るものなのだな? 」
快感と恐怖にまみれ上半身を剥き出し、股を濡らす姿それは犬そのものだ。
血塗れの顔が印象的に狂っている証明。
「お前の生きた理由も生きる理由も興味など無い。 風吹けば桶とも言うな? お前の命を終わらせる私が贈り物をしよう 」
ハンカチと言う文化も気に入ったものでね。
これを地面へ落とすだろう? 聞えるかこの音が?
「き、こえる…… 」
「ぴあのと言うそうだ、革命だよ! 素晴らしい 」
「陰陽師でありんす? 」
「違うと言っておるだろう、興味も無い事だ 」
月夜が私達の出会いを歓迎したな、実に大きくまるい!
見えるか蘭丸の刀身が?
「きれい…… 」
強い光、丸い月を背景に蘭丸で桶の女を切り落とした。
左腕、胴体、右手といった具合に斜めに一線したのさ。
泣いて綺麗と言った顔の正気具合を見ると実に良い瞬間だった。
人として殺してやったのは優しさかなと考える。
「あちきは全て奪われて、こんな風に殺されて。 あちきはなんでありんすか? 」
下衆として殺してやったもの、まだ生にしがみつくのか?
切り捨てた上半身の切り口から血液とケシ坊主の液が流れて落ちて、桶の女の血溜まりに混ざり合う。
煮えた熱湯の如く混ざり合った何かはまた上半身へ返り下半身を生やした。
「ほう? こうして壊れた人間を見たのは初めてだ 」

下半身は蜘蛛になり上半身からは人、切り捨てた腕もまた生えている。
ピアノの音がケシの花の山々を花弁と共に包む。
「あちきは不幸でありんす 」
「ほう? それは可哀相に、どれ噺を聞かせてくれ 」
「あちきは本が好きだった 」
どこにでもいる女だった……
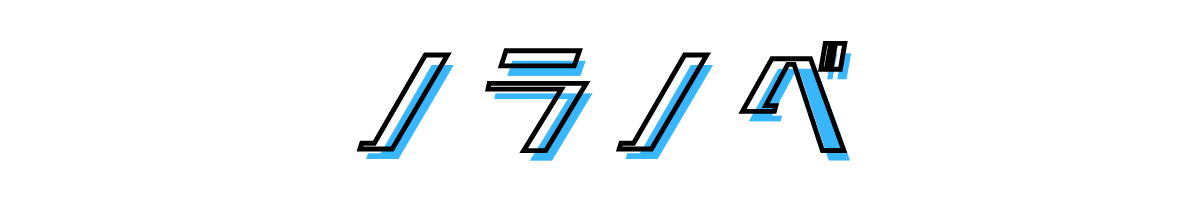


コメント